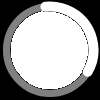
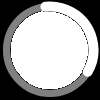
「萩色の旅」~萩に来て新しい萩の風を感じてみませんか?
新説・萩焼開窯前秘話~〝毛利氏によって隠された萩焼のルーツ〟
高麗焼「井戸茶碗」(枇杷色・黄色系統)は異国陶工たちが日本で焼いた和物茶碗で、そのルーツは須佐神山(黄帝信仰)にある!!

武将たちが天下一と愛でた高麗焼「井戸茶碗」は、朝鮮半島で焼かれた─と多くの公的・私的立場の学芸員が結論付けている。しかし、確証がない現状の中では「井戸茶碗」の制作地を朝鮮半島と判断することは危険である。その昔、日本人は中国文化を吸収して茶道を誕生させた。侘茶の始祖・村田珠光が好んだ青磁茶碗系統は、中国南部福建省がルーツとされるが、明貿易が盛んだった室町時代には大内氏が和物茶碗を焼くため、まず最初に中国南部の陶工を日本に連れて来て、その後、朝鮮半島からも高麗焼の技法を持つ陶工を連れて来て、日本国内で「井戸茶碗」を焼かせていた可能性がある。珠光好みの黄色系統の茶碗が焼かれた窯所、今も室町時代の古窯は未発見なのだが、須佐神山・黄帝社及び唐竹が多くみられる唐津谷にありそうだ。なぜなら、須佐唐津焼の起源は、古くから大内氏の頃から開窯されていたと言われてきたからである。珠光が好んだ当時の唐物茶碗の造形美を元に、「古(小)井戸茶碗」や「大井戸茶碗」が誕生したと考えられる。「井戸茶碗」(枇杷色・黄色系統)から、黄帝の象徴である黄龍が天に飛翔する姿をみて、武将たちは賞揚。多くの高麗焼「五龍の井戸茶碗」は、大内氏が勢力を誇った時代、須佐唐津と肥前唐津の2か所で焼かれた可能性が高い。その後、肥前唐津では、高麗茶碗と見紛う≪奥高麗茶碗≫と呼ばれる井戸形茶碗が焼かれたとされる(焼成窯所不明)が、上方(御所)からすれば、須佐唐津の奥にあることから≪奥高麗≫と呼ばれていたと思われる。古田織部の茶会(萩焼開窯直前)には、≪今高麗茶碗≫が登場。さらに、高麗焼「井戸茶碗」と見紛う井戸形茶碗(枇杷色・黄色系統)が萩焼草創期に焼かれている(焼成窯所不明)ことに注目。萩焼の開祖・李勺光の名前は、黄帝(北極星)に仕える勺(柄杓)と光(星)= 北斗七星と解釈すれば、優れた中国陶工(窯大将)であり、李敬はその中国陶技に敬意を払う朝鮮陶工。李一党の末裔・李勺光と李敬は、須佐神山から萩唐人山に移り開窯。その後、さらに李勺光は萩唐人山から毛利秀元の長府に移り松風山で開窯。須佐神山、萩唐人山、長府松風山、この3箇所を繋ぐと、〝萩焼のルーツ〟が見えてくる。すなわち、萩焼井戸形茶碗のルーツは須佐神山(黄帝信仰)にあると言う隠された萩焼420年の真実を解放する。
三輪正知
光悦茶碗研究家。
天皇を守護する近衛騎兵と近衛歩兵を先祖に持つ尊皇のおちゃわん屋・三輪清雅堂4代目当主。
令和7年9月26日(金)地元情報新聞「スポット山陰」一面で紹介されました。